2024年8月某日カブトムシを観察していると、オス同士がくっ付いてもぞもぞ動いてました。
喧嘩をしているのかなと思い、よくよく観察してみるとオス同士で後尾していました。
昆虫系のYouTubeを見たり、ブログなどでオス同士が後尾するということ
を聞いたことはありましたが
自分の飼っているカブトムシのオス同士が後尾しているのを発見した時はとても驚きました。
カブトムシのオス同士が後尾することのデメリット
カブトムシのオス同士が後尾することに、ほぼメリットはありません。
本人たちが良い気持ちになっていたら別ですがデメリットしかないはずです。
カブトムシのメス側のオスのデメリット
カブトムシのメス側のオスとは、普段はメスがされることをされるオスのことです。
受け手のことです。
カブトムシのメスはお尻に後尾器を突っ込まれても大丈夫な体になっていますが、
オスのお尻はそのようになっていません。
後尾器がお尻の穴に突っ込まれるので内臓が傷つく可能性が高いことです。
内臓が傷つき最悪の場合は死んでしまいます。
カブトムシのオス側のオスのデメリット
カブトムシのオス側のオスとは、普段はオスがすることをするオスのことです。
やり手のことです。
後尾器をお尻に突っ込むみ、腸にハマってしまい、もぎ取れてしまうこともあるようです。
もぎとれてしまうとすぐに死んでしまいます。
カブトムシのオス同士が後尾する理由
諸説ありますが、主に下記の通りです。
- メスと間違えて後尾してしまった事故。
- カブトムシもジェンダーレス社会。
多くの場合はメスと間違えてしまって事故で後尾をしてしまったケースが多いようです。
私の飼育していた環境は、繁殖を制御するためにコンテナボックスにオスだけを飼育する環境にしていました。
オス同士を密集させると、この様な事故が起こるケースも高くなるようです。
カブトムシをオス同士で一緒に飼育するデメリット
カブトムシをオスだけでまとめて飼うと後尾以外にもデメリットがあります。
カブトムシは喧嘩っ早いのですぐに喧嘩します。
喧嘩をすると、体に怪我をして長生きができません。
頭と体がもぎ取れるまで喧嘩をすることもあります。
カブトムシのオス同士を後尾させない方法
カブトムシを1匹づつ個別で飼うか、オスとメスのペアで飼うかのどちらかで飼う必要があります。
オス同士が出会わなければこの様な事故は起きません。
飼育に手間や費用がかかるかもしれませんが、カブトムシの快適な環境作りが大切です。
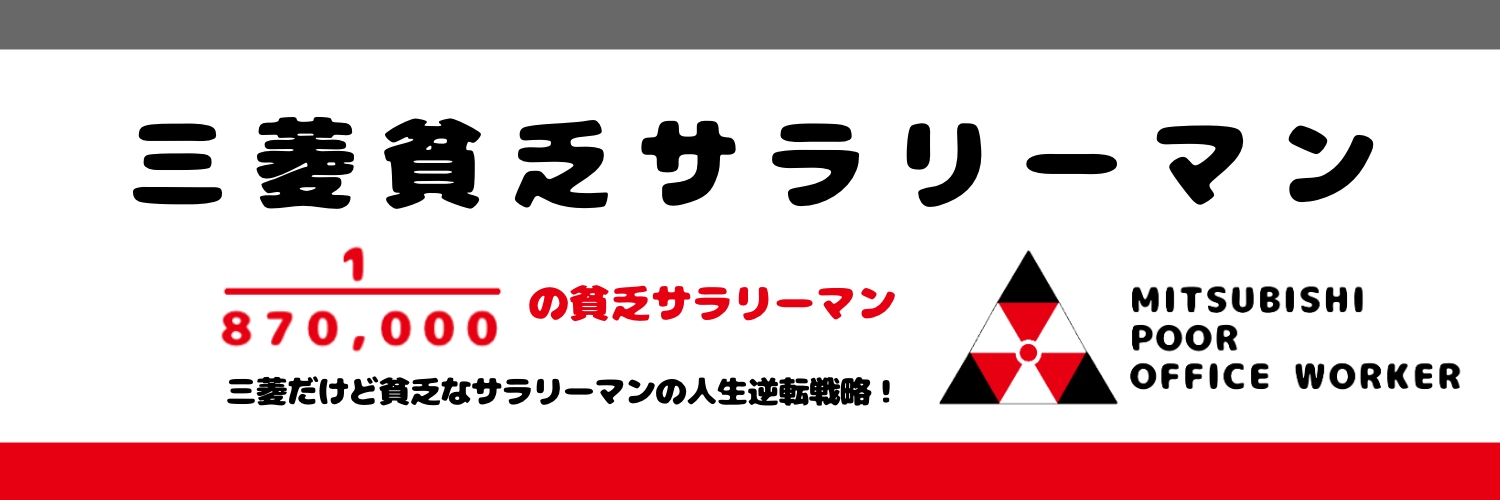



コメント